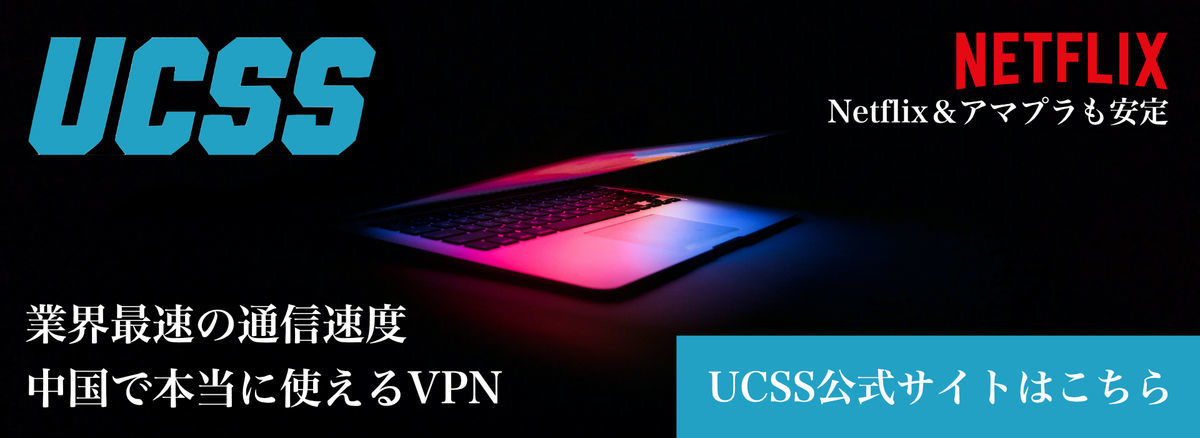近年中国では環境に優しい便利な交通の足として、電動バイクが普及しており、街中は電動バイクであふれている。なぜ、ここまで電動バイクが発展したのか、中国での普及の要因、日本で普及することはあるのか?について考える。
また、実際に中国で購入した電動バイクの使用感(バッテリー持ち、免許についてなど)をレポートしてみる。
中国で電動バイクが普及した要因
運転免許証が必要ない・規制が少ない
日本では免許証が必要であり自賠責加入やヘルメット着用が義務となるが、中国では自動車やオートバイに対する規制が適応されない。その為、自転車感覚で乗ることができるのである。
電動バイクの所有は購入時の登録番号のみで、税金や自賠責が必要ないということで維持費の有無は大きなポイントです。
運転免許証が必要ないということで、交通ルールに詳しくない人たちも運転をすることになり、交通違反やマナーが悪い場合も多く、交差点などでの事故は頻繁に見かけるのが現状である。電動バイクの法的規制は各省でかなり異なるという話も聞きました。
中国としても交通安全のために警察官を多く動員したり、今後は運転免許証を義務付けようとしているようだ。
価格が安価で買いやすい
電動バイクの価格帯は、安価なものだと約2万円から販売されています。ローンも組めるようで多くの方が気軽に購入可能となっています。
「小牛电动(niu)」という企業の製品は、国際的なプロダクトデザイン賞である「レッド・ドット・デザイン」賞、米国のデザイン賞「IDEA」賞や日本の「グッドデザイン」賞を受賞するなど、世界各地で高い評価を得ているオシャレなバイクも約7万円ほどで購入することができます。電池は世界的に定評があるパナソニックのセルを使用、モーターはドイツのBOSCH製となっており品質もかなり評判が良いです。

【小牛电动】https://www.niu.com/
大気汚染・渋滞緩和対策
中国は自動車が増えすぎたことが問題となっていて、大都市では渋滞緩和や大気汚染対策として、車のナンバーに応じて走行規制がかけられたり、オートバイの乗り入れが禁止されたことで、電動バイクが一気に地位を確立したと考えられる。
中国で実際に購入・乗ってみた
電動バイクの店へ

中国の大手電動バイクメーカーで有名な「雅迪」「小刀」「小牛」などをはじめとした多くのブランドが通りに並ぶ場所へ。
最初はふらふらと各店舗を散策。各社で様々な長所を打ち出し販売を行なっている。「バッテリーが0になっても走る電動バイク」「どこで壊れてもすぐに駆けつけて修理を行なうサービス」「盗難被害でも安心の補償」など面白いキャッチフレーズが飛び交う。
最終的に選んだのは、電動バイクメーカーとして歴史のある「雅迪」というブランド。走行距離も満充電で約50kmのモデルが多く、補償も充実しており、デザインもシンプルであるが安っぽさはない。

店内には、電動バイクがずらり。なかなかオシャレで清潔感もあります。店内に入ると店員が凄い勢いでおすすめしてくれます。
モデル選びから購入まで

カラフルなデザインで、若者からも人気な移動手段となっています。サイズも豊富なので悩んでしまいます。

こちらは可愛らしいモデル。遠出せずに街中をスイスイと走るなら、このサイズ感はかなり便利そう。重量も軽いので女性の方は小さいものに乗っている方が多い気がします。日本でも小さいモデルは人気が出そうな印象を受けました。

私が選んだのは、上記のモデル。2人乗りが可能で収納も多く、約50kmは走行可能とのこと。色が大人っぽくて気に入りました。ライトのデザインも他とは違ってポイントです。

操作類は簡単です。ギアは2段階あります。最高時速は約48km/h。
速度表示、バッテリー残量が確認できます。シンプルですが見やすいので問題なし。

後ろからのフォルムも良さげです。結構大きめな電動バイクとなっています。
価格ですが、なんと約4万円!!かなりお買い得でした。
電動バイクの使用感は?
ここからは使用感をザッとまとめてお伝えします。
・満充電約50kmはギリギリ達成可能。バッテリー持ちが良い。
・パワフルで坂道も快適。
・電動バイクなので静かで臭くない。
・ブレーキの効きも良く心配なし。
・荒い道でも安心、振動も意外と抑えている。
・バイクのバッテリーでスマホの充電が可能。
・免許証不要、規制も少なく自転車感覚で乗れるので便利。
このように価格的に考えても、かなりコスパが良く満足度の高い商品に感じています。中国だと移動手段してはかなり便利で、中国だと2輪専用道路が多くあるのも非常に便利で快適。
バッテリー自体は心配する必要は無さそう。現在走行距離は500kmを超えたが変化はなし。(バッテリーの持ちについては使用経過をチェックしてみる)
電動バイクの日本進出は?
日本の商社が輸入して販売しているようですが、結構価格が高くなっているのが現状です。
日本進出があるのか?ということに関しては日本の場合、免許証(普通免許、原付二輪など)が必要なことや、日本国内での電動バイクの販売価格が高くなっている為、同価格帯で日本製の優れたバイクが既に多く販売されている点などが指摘されています。他にはバッテリーの廃棄問題などがあり、電動バイクの日本進出が進んでいないと言われています。